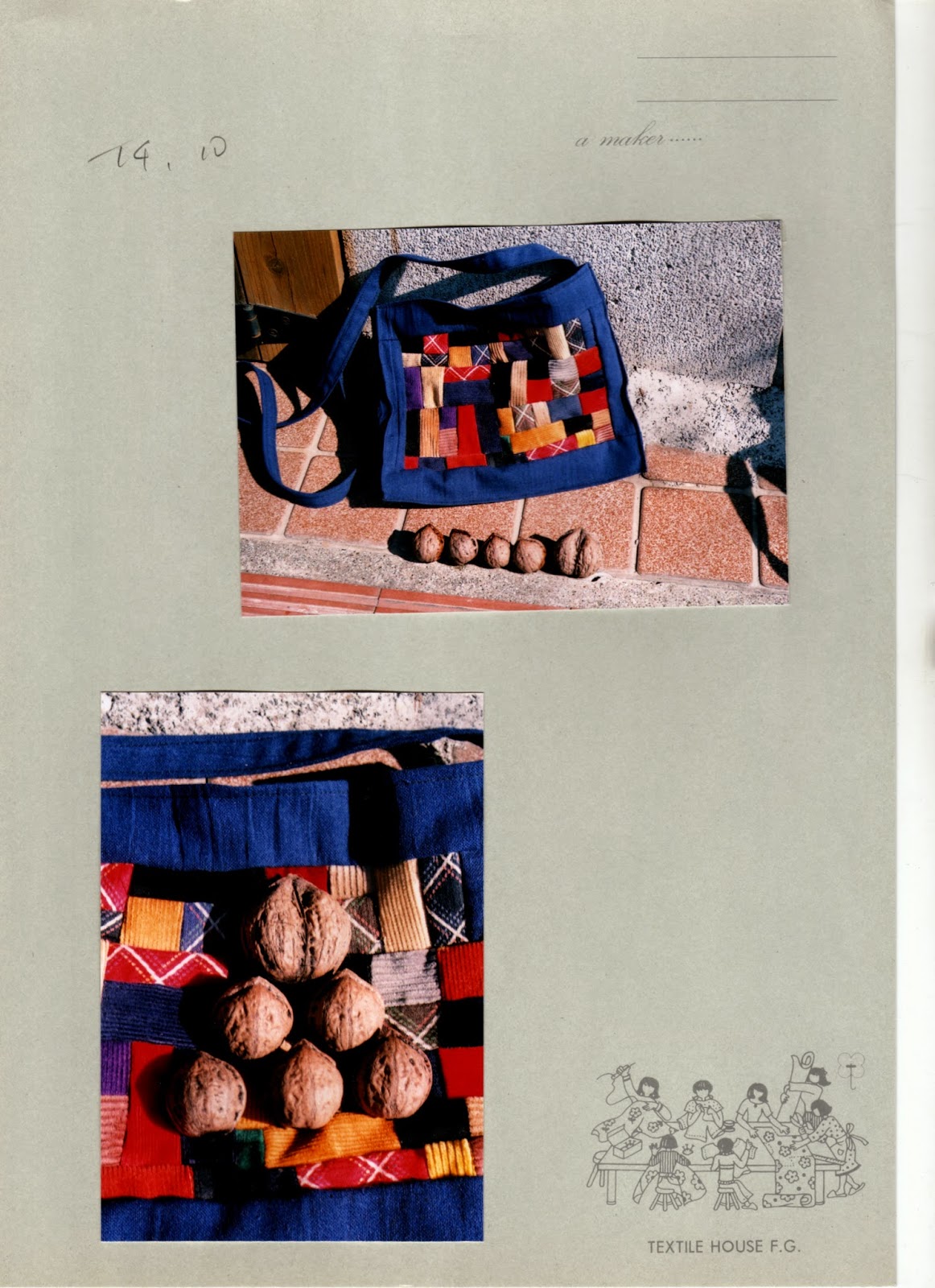戦前の養蚕
昭和10年の東郷村の総戸数は772戸 内養蚕を営んだ農家は 564戸(総戸数比78、1%)に達していた。又 村内の部田(ヘタ)養蚕組合の記録によれば『純農村なれども米麦の収入よりも 寧ろ養蚕による収入が多い傾向に有って 養蚕業の盛衰は 農家経済は勿論 村財政に多大の影響を与えつつ有り。・・・とあり。
戦前の農家の食生活は、米は換金作物であるため、今日の様な食生活でなく 下の東郷村の各種記録を見ると昭和5年の生糸相場の暴落は 繭の値段に大きな影響を与えたであろう。又 レーヨン・ナイロンの生産が始まり輸出生糸の減少による影響も有り、戦前の農村生活は大変であったと推察される。
最近の養蚕
家畜化されていた昆虫『蚕』に、遺伝子組み換え他 色々な開発・改良で衣料以外に食品・化粧品・医薬品ほか多用途に利用される様になり現在は非常に注目される分野だ。
又、身近な話題としては、東郷町のお隣天白区植田の『特定非営利法人 マルベリークラブ中部』の猿投・足助地区での活躍がある。
下は、戦前の 簇(マブシ)作り機と簇折り機
豊橋の資料館のもの
東郷町の資料館のもの